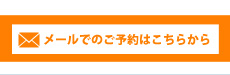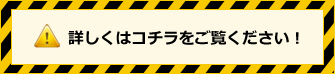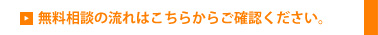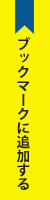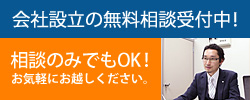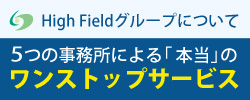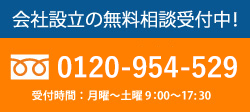建設業
建設業の今
平成23年3月11日の東日本大震災以降、特に東北で建設業を営む社長様は、実に多忙な日々を過ごしていらっしゃると思います。
ようやくひと段落ついた方、全く変わらず忙しい方、以前にも増して忙しい方、様々かと思います。
こうした状況の中、今が、許可取得のチャンスかも知れません。
日々の仕事に追われてしまい、事業内容を振り返ることもできなかったここ数年で、

こういった積み重ねが、もしかすると、建設業の許可、さらには業種追加の要件をクリアしている可能性があります。
震災から3年が過ぎましたが、震災後の処理はいつか必ず終わりますし、終わらなければなりません。その時に備え、今、もう一度事業を振り返り、建設業許可取得をご検討されてはいかがでしょうか?
震災後の処理がすべて終わったそのとき、本当の復興に向けて、いち早く体制を整えることができるのは社長様かもしれません。
どんな場合に建設業許可が必要なのか
建設業を営む場合、以下の「軽微な工事」に関しては、許可は必要ありません。
特に、最近は「取引先から『建設業許可がないと取引できない』と言われた。」とご相談にみえる方が増えております。
この機会に、建設業許可取得をご検討されてはいかがでしょうか。
建設業許可を取得する為には、これからご説明しますが、大きく分けて「5つの要件」があります。
確かに、「考え方」「証明するための書類」いずれも複雑です。
その結果、ご相談にいらっしゃるお客様のうち、

と思い込んで、許可取得をあきらめそうになっていた方がたくさんいらっしゃいます。
建設業許可を取得するための5つの要件
経営業務の管理責任者を確保できること
法人であれば役員のうち1名、個人事業であれば事業主本人が、建設業許可業者の役員又は個人事業主としてとして5年~7年、経営を管理した経験があることが求められます。
許可申請を行う際は、過去の経験を工事請負契約書等で証明する必要があります。
専任技術者を営業所ごとに置いていること
営業所ごとに、業種に応じて「土木施工管理技士」「電気工事士」「建築士」等の資格者を設置することが求められます。
資格によっては、1年~5年の実務経験が必要となる場合があります。
逆に、資格者を持っていなくても、10年の実務経験を証明できれば、専任技術者として認められる場合もあります。
請負契約に関して誠実性を有していること
建設業法、建築士法、宅地建物取引法、その他法令上、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許の取消し処分や営業停止処分を受けて相当期間を経過していない場合は、誠実性を満たさない者と扱われます。
財産的基礎又は金銭的信用
法人の場合は、直前の貸借対照表の「純資産合計」の額で判断されます。
個人事業の場合は、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等が求められます。
欠格要件に該当しないこと
法人については役員全員、個人事業の場合は事業主個人について、法務局発行の「登記されていないことの証明書」、市区町村長が発行する「身分証明書」を求められます。
尚、上記は要件についての基本的な考え方をまとめたものです。実際の申請にあたっては、かなり細かな検討が必要となりますので、是非、当事務所にご相談ください。
申請時必要書類(基本的なものです。状況に応じ、他の書類が必要な場合もございます)
経営業務の管理責任者の確認書類
専任技術者の確認書類
役員の確認書類(法人の場合)
その他確認書類
許可取得後の義務
建設業許可を取得した建設業者には、いくつかの義務が発生します。
その義務を果たさなかった場合は、建設業法に違反することとなり、様々なペナルティを受けることになります。
最悪は、「許可の取り消し」という事態も考えられます。
しかし、その反面、これらの義務をきちんと履行していれば、「許可業者」としての絶大な信用が発生するとも言えます。
主なものを整理してみます。
工事現場への技術者の配置
「主任技術者」
建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、請負金額や元請・下請であるかにかかわらず、工事現場に「主任技術者」を配置しなければなりません。
この主任技術者は、1級、2級資格者、または実務経験者である必要があります。
「管理技術者」
発注者から元請で工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者に代えて「管理技術者」を配置しなければなりません。主に特定建設業の許可業者について問題となります。
雇用の問題
主任技術者、管理技術者は、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
具体的には、以下のような場合は認められません。
一括下請負の原則禁止
工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与を行わず、下請に工事の全部または一部を請け負わせることは、「一括下請負」として原則として禁止されています。
一括下請負とは
帳簿の備付け
建設業法では、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を各営業所ごとに備えておく必要があります。
帳簿は5年間保存する義務があります。
各種届出
一定の事項に変更があった場合は、所定の期間内に管轄先に届け出なければなりません。
事業年度終了後4か月以内に届け出る必要があります。
報酬、費用
| 内容 | 報酬(税込) | 収入証紙等実費 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(新規・知事) | 165,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可申請(新規・大臣) | 198,000円~ | 150,000円 |
| ※申請時の実務経験証明作成 | 11,000円(1年分) | |
| 建設業許可(更新・知事) | 77,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可(更新・大臣) | 77,000円~ | 50,000円 |
| 建設業業種追加申請 | 55,000円~ | 50,000円 |
| 建設業決算変更届 | 38,500円~ | |
| 経営状況分析 | 33,000円~ | 12,340円 |
| 経営事項審査 | 55,000円~ | 11,000円~ |
| 入札参加資格登録申請 | 33,000円~ | |
| 各種変更届 | 22,000円~ |
許可に要する期間
新規知事許可は、申請受理後約1か月、大臣許可は約4~6か月となっております。